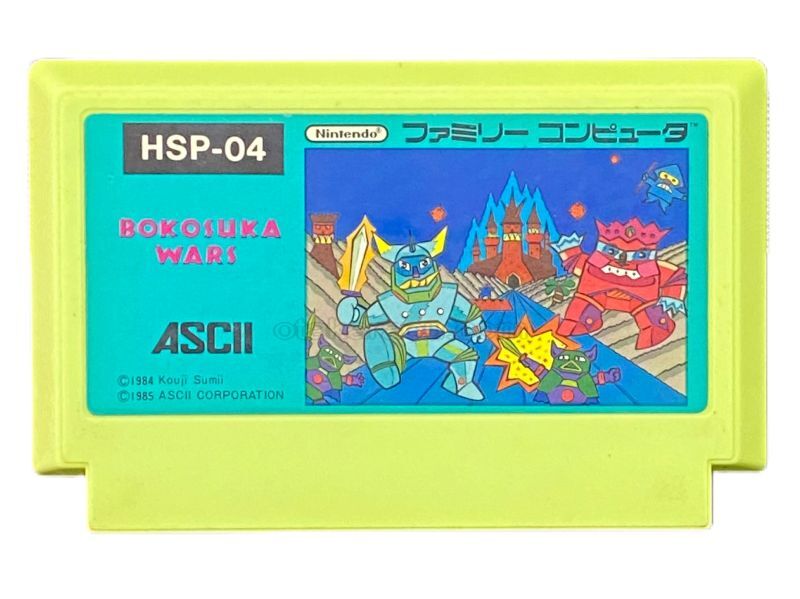2月6日
私の実家の様子がLINEで送られてきた。
この積雪量を見るに、優に60cmはあると推測される。
私の記憶を辿っても、20年以上前でないとこれほどの積雪は記憶にない。実家には私の両親が住んでおり、雪かきをしないといけないことを考えると、無理せずにやってほしいと思うばかりだ。幸い、私の弟が近くに住んでいるので応援を要請したいところだ。
私は高校を卒業するまではこの実家に住んでいた。当時、大雪に見舞われた時の事を思い出してみる。この地域の学校は大雪という状況がそれほど珍しくはなく、大雪が原因で下校が早まったり、休みになるということは異例中の異例だった。
ただ、中学時代のあの日は少々、状況が異なっていた。私の数少ない中学時代の記憶。
雪が降りしきる朝は珍しくはなかったが、登校して教室に入ると生徒が半分くらいしかいなかった。担任の話によると、親や本人の判断で登校を諦めたとのことだった。登校してきた生徒も普段は自転車に乗るところを徒歩にしたり、親に車で送ってもらったりだった。私は気合で2.5kmほどの道を自転車で登校したのだった。
生徒の半分近くがいなくても授業は行なわれた。当時の教育体制とはそういうものだ。この日は状況を見かねてか、午前中の授業が終わった時に、午後は大雪のため各自下校ということになった。
私は下校の途中で貴重な体験をした
午後になっても降雪の勢いは全く衰えなかった。車道のアスファルトはどこからも顔を見せることはなく、車のタイヤで踏み固められては新しい雪が積もることを繰り返す。やがて車の交通量が減り、踏み固まった雪の上に新雪の層ができる状況になった。
下校指示が出てから少しの間、教室の窓から外を伺っていたが、まったく止む気配を感じられず、帰宅を決断した。
通い慣れた道であっても、雪で一面を白く覆われた状況には多くの危険が存在する。まして、積雪が50cm以上となると、通学路に存在していた構造物の高低差をも消してしまう。
田舎の道で特徴的なのは、道とその両側にある水田の間に用水路が存在する点だ。用水路は浅いもので30cm、深いもので100cm以上ある。そこに落ちないための網やガイドのような構造はなく、ただの川なのだ。大雪が降ると、この川の上を雪が覆ってしまい存在が分からなくなる。所謂、落とし穴のような状況になるのだ。私は両側に落とし穴がある道を帰るわけだ。
登校時に乗ってきた自転車には乗ることができず、手で押して家路を急ぐ。2.5kmの道を自転車を押して帰る。これだけを考えると特に大したことはないと思っていた。しかし、思わぬ状況に陥ってしまう。
体の疲れが著しい。
気づいた頃には息があがってしまい、ほとんど動けなくなっていた。原因は私が異常に厚着をしていたこと、自転車の車輪とブレーキの間に雪が詰まってしまい、タイヤを回す抵抗が大きくなり、結果、前方へ押す力が何倍も必要になっていたと後になって気づいた。トリッキーでこそあれ、そんなに長くない道のりを自転車を押して帰るだけという考えに胡坐をかき、体力を奪われてしまうことにまったく頭が回っていなかった。さて、動けないけどどうしようか。
少しだけ横になってみるか。。。
この考え以外に何も浮かばなかった。今思い返しても不思議なのだが、まるでトイレに行きたくなったからトイレに行くというレベルで判断を下してしまった。用水路のない道路脇に自転車を放り投げ、新雪の上に横たわった。動けなくなるほど運動をしていたせいで、体は暑いくらいにポカポカだ。大きく深呼吸を数回したところで、どうやら眠ってしまったようだ。
寒さで目が覚める。
どのくらいの時間眠っていたのか定かではないが、日は幾分傾いていた。体や自転車に積もっている雪の量から考えると1時間くらいだろうか。
豪雪地域の寒さというのは一味違う。朝は痺れるように寒く、長時間寒さにさらされると、鈍痛に近い感覚が寒さを上回る。まさに体中鈍痛に襲われ、呼吸もごく浅くしかできない状況に陥っていた。
もう一度横になるという選択肢は不思議と湧いてこなかった。何とかして家に帰らねば。もはや車道を走る車は一台もなく、私は自転車をその場に置いたまま歩いて帰宅することにした。700メートルほど先に自動販売機がある。そこに辿り着いてあったかいジュースを飲むことだけを目標にゾンビのように時に声を出して進んだ。ようやく自動販売機に辿りつき、あったかいミルクココアを2本買った。1本は暖を取るため、1本は飲むため。自動販売機の出口から取り出したココアは暖かく、冷え切った手に持つと、鈍痛を感じる。鈍痛に耐えているとやがて通常の心地よい暖かさが伝わってくる。
力を取り戻した私は無事自宅へ生還した。
冬山で遭難する人はこんな感覚なのだろうか。私が眠ってしまったような感覚が近しいのなら、多くの人が想像している感覚とは異なっていると思う。私も以前から凍死の危険性についての知識はあった。しかし、直面したときに眠ると危険という選択肢が消えているというのが正しそうだ。そしてまた、思いのほか簡単に眠れてしまうのと、心地よさすらあったのだ。
おー怖っ。